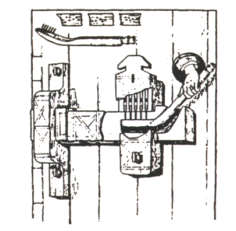
図1
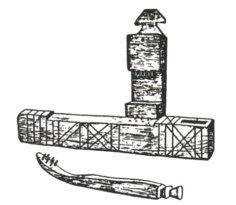
図2
★古代の鍵と錠
エジプト錠(紀元前2000年)
人間が何か財産を持つようになったときから、それを守るための工夫がされたであろうことは容易に想像がつく。それが錠という形を取った最古の物は「エジプト錠」と呼ばれている。[図1]の様な木製の錠及び鍵だというのが今日の定説である。この錠の構造は、かんぬき(閂)と錠本体とを数本のピンで動かないようにしておき、外から錠を開ける(解錠する)ときは、[図2]のように扉の穴から鍵(カギ)を差し込んで、カギでピンを押し上げて閂を動かす仕組みになっている。
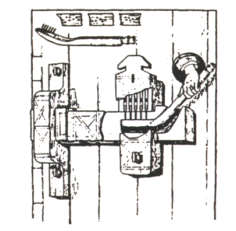
図1
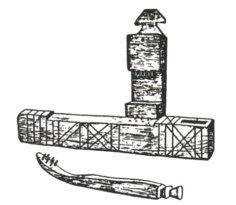
図2
ギリシャの鍵と錠(紀元前1000〜300年)
ギリシャ時代の初期には扉の締りとして、かんぬき(閂)を革紐や綱で縛って複雑な結び目を作る方法がおこなわれていて、その結び目はその家の主人しか解けないものであった。この錠は安全度においてあまり期待できなかったと思われる。その後ギリシャ時代の後半には、エジプト錠の原理を応用したもので 、さらに精巧な「パラノス錠」が考案されるようになった。[図3]
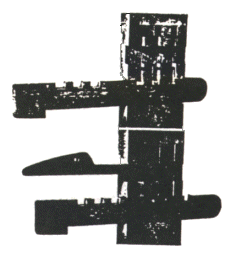
図3
ローマの鍵と錠(紀元前750〜30年頃)
ローマ時代の鍵のほとんどが鉄製であったため、完全な状態のものは発見されていないが、発見された青銅製の閂から、この頃も「エジプト錠」や「パラノス錠」と同じ原理の錠が使用されていたようである。また、この時代のは南京錠(padlock)が使われ始めたようで、地中海沿岸地方から近東にかけて流行しており、とくに中国では広く使われていたようである。日本の正倉院に保存されている「海老錠(えびじょう)」と呼ばれる南京錠は、この頃のものと思われる。[図4]ローマでは、指輪のように指にはめる南京錠の鍵が使用されていたようである。[図5]また、ローマ時代には現在の「ウオード錠」に近いものが広く用いられるよいになったらしい。
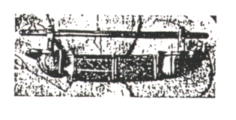
図4

図5
★中世の鍵と錠
中世のヨーロッパは力が社会を支配した時代で、錠も破壊に強い大型のものが使われていた。その形式は、「ウォード錠」といわれるもので錠側に障害物(突起)(ward)を多様に設け、鍵は複雑な刻みめ(きりぬき)がほどこされた大型のものであった。権力者は、次第に鍵模様の精巧さや美しさを競うようになり、渦巻模様、組合せ文字、注文主の紋章などを表したものなどが現れ、鍵が権力や地位の象徴になった。今日でも都市が善意の意味で外国の都市や客に礼儀的な都市の鍵をおくったり、渡したりすることが行われています。鍵作りの職人にも芸術的で優美なものを作る者が現れ、時計はこれらの職人が作り始めたといわれている。しかし、錠そのものの進歩はほとんど見られない暗黒時代といえます。
★近世の鍵と錠
産業革命前後に鍵と錠も大きく進化しました。僅か150年位の間に各種の形式の錠が出現し、しかもその詳細を知ることが出来る。次に時代を追ってその概要を説明します。
<BARRONのレバータンブラー錠>(1778年)
イギリスのRobert Barronはレバータンブラーを発明した。これは現在の「レバータンブラー錠」の原型といえるものである。
<BRAMAHの錠>(1784年)
イギリスのjoseph bramahが発明した錠で、当時のオーソドックスな錠の方式と全く違った独創的なもので、広く名声を得たといわれています。
<CHUBBレバータンブラー錠>(1817年)
イギリスのChubbはレバータンブラー錠で、不法に解錠されないような装置があり、かつ不法に解錠しようとしたことが判明できる装置の付いたレバータンブラー錠を発明した。現在でもChubbの錠はこれと同じ装置が付いています。
<YALEのピンタンブラー錠>(1848年)
米国の銀行錠製作作者(Limus Yale)は「エジプト錠」や「ローマ錠」の原理を利用した錠を発明した。これは、既にほとんど現在のピンシリンダーの機構に達している。鍵違いが多いこと、誤動作も無く防犯性に優れていることなど優れた特徴を有しており、約一世紀半が経過した現在でも、米国は勿論、世界各地において、錠のシリンダーとして主流を占めています。その他この頃には「ディスクタンブラー錠」「符号錠」「タイムロック」など現在の錠の殆どのものが出揃って現在にひきつがれています。
★近代から現代へ
エールのピンシリンダーを主体にしたアメリカの錠とレバータンブラー錠を主体にしたヨーロッパの錠とが近代から現代に向けて発達し、19世紀末には、現在ある錠の形式や種類はほとんど出来上がり、それ以降は素材が変わったり、生産方式が(手造りから工場のライン生産へ)変わったためのマイナーチェンジにすぎません。